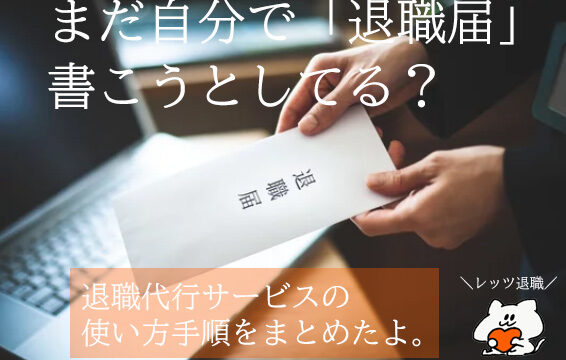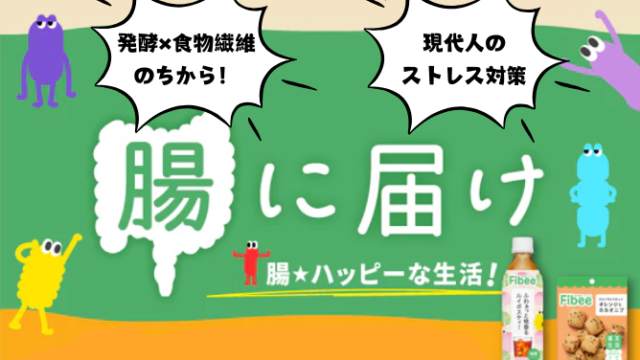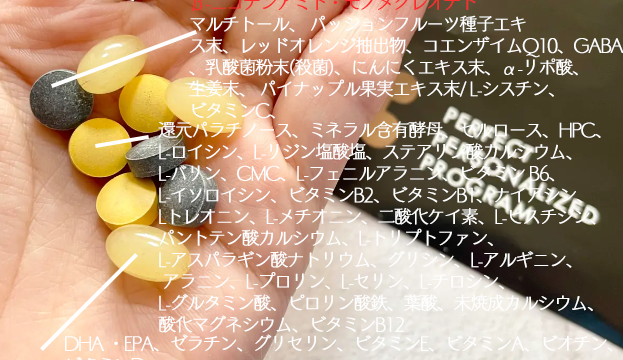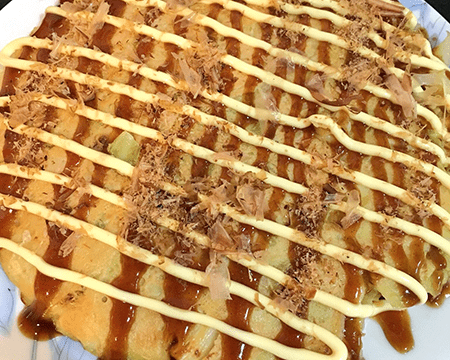急な訃報で慌てないために。お通夜と告別式の違いから、香典の相場、服装のマナーまで、葬儀参列の基本を分かりやすく解説します。故人を偲び、遺族に寄り添うためのガイドになれば幸いです✨
お通夜と告別式、それぞれの意味と目的

お通夜:故人と親しい人々が最後の夜を共に過ごす場
- 親しい家族や友人が集まり、故人の思い出を語り合う
- かつては夜通し故人を見守る儀式だったが、現在は半通夜が一般的
- 通夜振る舞いがある場合も、長居は避けるのがマナー
お通夜は、故人と親しい間柄の人々が集まり、最後の夜を共に過ごすための儀式です。
かつては、故人の霊が悪霊から守られるよう、文字通り夜通し灯りをともして見守るという意味合いがありました。しかし現在では、葬儀場などで行われることが多くなり、1〜3時間程度で終わる「半通夜」が主流となっています。
僧侶の読経や焼香の後、地域によっては「通夜振る舞い」と呼ばれる食事が提供される場合があります。 これは故人を偲ぶための席なので、長居は避けるのがマナーとされています。
お通夜は、故人との思い出を語り合いながら、ゆっくりお別れをするための時間なんやね。しんみりとした雰囲気を大切に、遺族への配慮を忘れんようにせな。
告別式:故人に最後のお別れを告げる社会的な儀式
- 故人の死を悼む人であれば誰でも参列できる
- 出棺前に行われる最後の儀式
- 火葬場へ同行するのは、一般的に近親者のみ
告別式は、故人との社会的なお別れの場です。
故人と生前に縁のあった友人・知人、仕事関係者などが参列し、最後のお別れを告げる儀式です。読経や焼香、弔辞の奉読などが行われます。
告別式後、出棺となり、火葬場へと向かいます。一般的に、火葬場まで同行し骨上げまで参列するのは近親者のみで、それ以外の参列者は出棺を見送ってお別れとなります。
告別式は、社会的なお別れの場やから、誰でも参列できるんやな。最後のお見送りやから、きちんとした服装で敬意を表すことが大事やで。
お通夜と告別式、どちらに参列すべき?
【基本】故人との関係性で判断する
- 親族や特に親しい友人:お通夜と告別式の両方に参列するのが望ましい
- 知人や仕事関係者:告別式に参列するのが一般的
故人との関係性が深い場合は、お通夜と告別式の両方に参列するのが最も丁寧とされています。
お通夜は、故人と特に親しかった人々が思い出を語り合いながら静かに過ごす場です。親族や親しい友人として参列することで、故人を偲び、悲しみに暮れる遺族を支えることができます。
知人や会社の同僚といった一般的な関係の場合は、告別式に参列するのが通例です。しかし、最近では仕事の都合などで昼間の告別式に参列できない人が増え、お通夜に一般の弔問客が訪れることも多くなっています。
故人と近しい間柄なら両方に行くのが一番丁寧やけど、どうしても都合がつかん場合は、どちらか一方に参列するだけでも気持ちは伝わるで。
案内状の確認や地域の慣習も考慮
- 案内状に指定があれば、それに従う
- 地域の慣習を事前に確認すると安心
葬儀に参列する際は、案内状に記載された内容や、地域の慣習も考慮することが大切です。
案内状に参列してほしい日時が明記されている場合は、可能な限りその意向に従いましょう。また、地域によって葬儀のしきたりが異なる場合があるため、不安な場合は事前に確認しておくと安心です。
例えば、一部の地方では、お通夜は近親者のみで静かに行うのが一般的な地域もあります。
案内状の確認と、その土地の習慣を尊重することが大事やな。失礼のないように、しっかり準備しときたいもんや。
香典のマナー:金額の相場・渡し方・注意点
- 金額は故人との関係性や自分の年齢、地域によって異なる
- 両方に参列する場合は、お通夜か告別式のどちらかで一度だけ渡す
- 香典袋の表書きや中袋の書き方にもマナーがある
香典は、故人への供養の気持ちと、葬儀費用の助け合いという意味合いを持つものです。金額の相場や渡し方など、基本的なマナーを押さえておきましょう。
香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢によって変動します。一般的に、親族であれば3万円~10万円、友人や同僚であれば5千円~1万円が目安とされていますが、あくまで相場です。
お通夜と告別式の両方に参列する場合は、どちらか一方で香典を渡します。二度渡すのは「不幸が重なる」ことを連想させるため、マナー違反とされています。 一般的には、先に参列するお通夜で渡すことが多いようです。
葬儀への参列は、ご自身の将来やお金について考えるきっかけにもなりますよね。「保険は本当に必要なの?」と疑問に思った方は、こちらの記事で詳しく解説しています▼
【保険はいらない】は本当?リベ大・中田敦彦が語る生命保険・医療保険の罠と本当に必要な保険3選
服装のマナー:弔事にふさわしい身だしなみ
- 基本は準喪服(ブラックフォーマル)を着用
- 急な弔問の場合は、地味な平服(略喪服)でも可
- アクセサリーや香水は控え、殺生を連想させるものは避ける
葬儀に参列する際の服装は、故人と遺族への敬意を表すため、派手なものは避け、黒を基調とした服装を心がけましょう。
基本的には、男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマル(ワンピースやアンサンブルなど)の「準喪服」を着用します。
急な訃報で駆けつけるお通夜など、喪服の準備が間に合わない場合は、黒や紺、グレーなどの地味な平服(略喪服)でも失礼にはあたりません。 アクセサリーは結婚指輪以外は外し、パールの一連ネックレス程度に留めるのがマナーです。香水も控えめにし、殺生を連想させる毛皮や革製品は避けましょう。
葬儀の服装は、おしゃれをする場やない。地味な色で、清潔感のある身だしなみを心がけることが、故人を敬う気持ちの表れやで。
お通夜・告別式に参列できない場合の対応
- 弔電(ちょうでん)を送る
- 後日、弔問(ちょうもん)に訪れる
- 香典を郵送する
どうしても参列できない場合は、弔電を送ったり、後日改めて弔問に伺ったりすることで、弔意を表すことができます。
お通夜や告別式に参列できなくても、故人を悼む気持ちを伝える方法はあります。
弔電は、告別式が始まる前までに届くように手配するのがマナーです。後日、お悔やみを伝えにご自宅へ伺う「弔問」の場合は、必ず事前に遺族の都合を確認してから訪れましょう。香典を郵送する場合は、不祝儀袋に入れたものを現金書留で送り、お悔やみの手紙を添えるとより丁寧です。
参列できひんくても、気持ちを伝える方法は色々あるんやな。弔電や後日の弔問で、しっかりお悔やみの気持ちを伝えなあかん。
まとめ
お通夜と告別式は、どちらも故人を偲び、遺族に寄り添うための大切な儀式です。それぞれの意味合いやマナーを正しく理解し、故人や遺族への思いやりを込めて参列することが何よりも大切です。急な知らせに戸惑うこともあるかと存じますが、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
実際に葬儀社を選ぶ際には、こちらの記事も参考にしてみてください。後悔しないためのポイントをまとめています▼
関西で後悔しない!葬儀社おすすめ人気ランキングTOP30【2025年最新版】
この記事を読んだ人はこちらも見ています
- 関西で後悔しない!葬儀社おすすめ人気ランキングTOP30【2025年最新版】
- 【保険はいらない】は本当?リベ大・中田敦彦が語る生命保険・医療保険の罠と本当に必要な保険3選
- 【2025年】LINEでバイト辞めるのはアリ?失敗しない退職代行の選び方&おすすめ3選